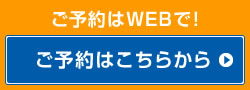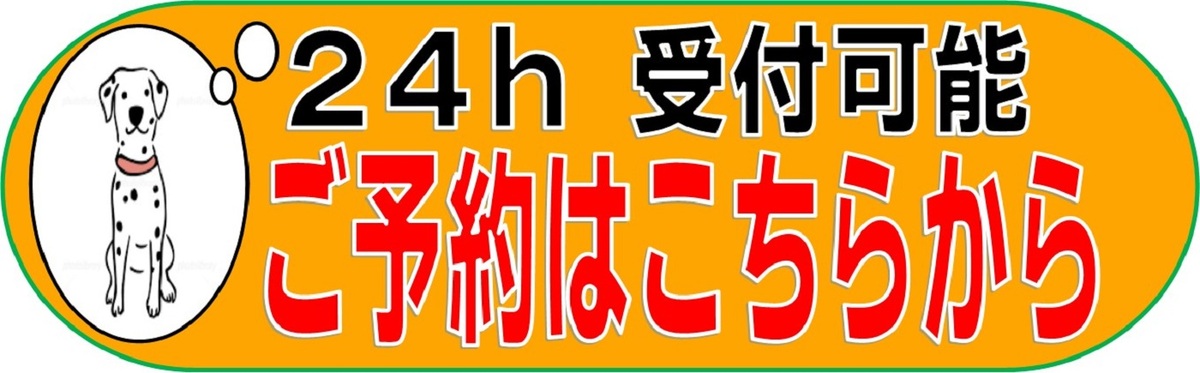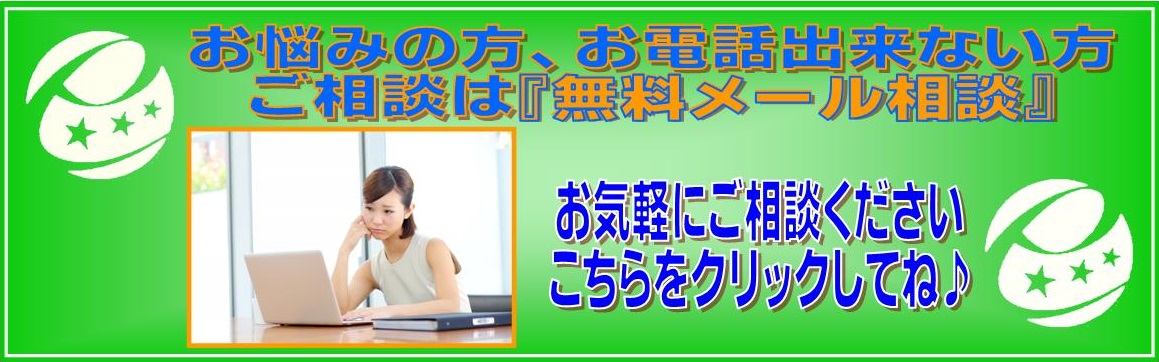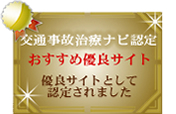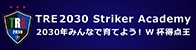スタッフブログ
骨折の早期回復③|エコルスタはり・きゅう整骨院
骨折の早期回復のポイント
- 機能的な固定法
- 患部以外の機能低下防止
- 適切な時期による機能回復リハビリ
- 睡眠・栄養
などが挙げられます。
今回は
3,適切な時期による機能回復リハビリについて
骨折や怪我をすると必ず各関節・筋肉の機能低下が起こります。
それをそのまま放置したままですと、スポーツにおいては
再負傷や新たな怪我の発生率は高まります
よく【捻挫癖】と言う方がいらっしゃいます。
それが正に機能低下を放置したままの状態です。
中高年の方は【ロコモティブシンドローム】に繋がります
この様な状態では再び筋肉・関節の機能低下による
二次災害が起こるため危険です。
ある程度骨が安定安定してきたら
動かす事により【血流があがります】
その結果、血液循環が上がれば
【栄養が沢山運ばれる】様になり
より、骨がくっつくスピードが上がる事が期待できます
更には当院では酸素カプセル・超音波・低周波治療器を
組み合わせることによりより細胞の回復を上げる
効果の高い機械を組み合わせて施術を行っております
骨折治療でお困りの方は是非、
ご相談【無料】・ご予約下さい

骨折の早期回復②|エコルスタはり・きゅう整骨院
骨折の早期回復のポイント
- 機能的な固定法
- 患部以外の機能低下防止
- 適切な時期による機能回復リハビリ
- 睡眠・栄養
などが挙げられます。
前回は 1.機能的な固定法についてお話させて頂きました。
今回は
2、患部以外の機能低下防止について
骨折をしてしまい、患部を固定されてしまった以上何もする事ができない…。
と思っている方が多いです。とは言えほとんどの方がそう思うと思います。
ですが、患部の機能低下を防止できる方法は沢山あります。
幹部とは言え折れている所へ直接ストレスがかからなければ良いですし、
患部以外にも上肢(腕)・下肢(脚)全体で考えれば、
動かさなくなると機能低下を招きます。
機能低下とは支える力が落ちたり、
本来出るべき力が出なかったり、
上手く動かせなくなったりetc...
骨折は患部がくっつけば完治でなく、当院ではきちんとしたパーツの
役割が全て出来るようになって完治として
お話させて頂いております。
患部の機能低下は固定した日から始まります。
同様に、拘縮や機能低下を最低限に抑える事もその日から出来ます。
骨折の早期回復でお悩みの方、早期回復ご希望の方は
是非、当院へご相談ください。
同時に当院の酸素カプセル+水素+電気治療器を
合わせた治療も大変効果が期待できます♬
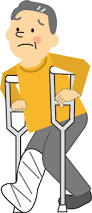
骨折の早期回復|エコルスタはり・きゅう整骨院
骨折の早期回復のポイント
- 機能的な固定法
- 患部以外の機能低下防止
- 適切な時期による機能回復リハビリ
- 睡眠・栄養
などが挙げられます。
それぞれもう少し、解説していきましょう
機能的な固定法
機能的な固定方法とは、時として手術による固定法であったり
何もかもぐるぐる巻きにした固定が良い訳でなく、
シーネ(添木)固定も状態によっては物凄く有効です
一番避けたいのは手術によるものでしょうが、
折れている場所や状態によっては
手術の方が完全に骨が付き、早い場合もあります。
そうでなければ、きちんと骨を接ぎ適切な
固定方法を行えば、早期回復に繋がります。
私共の言う早期回復とは、固定による拘縮や機能低下を
最低限に抑え、日常生活やスポーツ競技に復帰の事を言います。
骨折でお悩みの方は
是非当院で酸素カプセル+水素+電気治療器を使った
治療にご相談ください

交通事故治療の無料相談窓口設置しております~市川市南行徳エコルスタ整骨院~
無料相談窓口設置しております
事故に遭ってしまいました・・・。
- どのように手続きしてよいか解らない・・・。
- 検査機関はどこへ行ってよいか解らない・・・。
- 退院後のリハビリはどこへ行ったらよいか解らない・・・。など
事故により怪我を負ってしまうと患者様はどのようにしてよいか
解らない事だらけです。
当院ではそのような患者様のための
無料相談窓口を設置しております
交通事故による施術は自賠責保険によるものです
交通事故によるお怪我は自賠責保険による扱いになる為、
基本的には健康保険はご利用なれません。
過失割合にもよりますが
10:0でない限り、加害者・被害者もです。
健康保険は第3者行為によるものは全て
適応不可となります。

無料相談はメールでも承っております
ご連絡はこちらから
無料メール相談
交通事故によるムチウチ症治療が大切な理由~市川市南行徳エコルスタ整骨院
動きを取り戻す・正しく動かせないといけな理由
交通事故や乗り物などによる
ムチウチ症がなぜ
痛みが取れた後が大切かといいますと
損傷度合いも多きいムチウチ症は
首の動きを一瞬にして悪くさせます
首の動きはスポーツや
その他の運動においてとても重要です。

※実際、弓道やダーツなど姿勢を固定しているときも
偏頭痛、肩こり、首こりなどへつながります
それから、背中・腰~下半身までにも
筋肉への力の伝わり方が
交通事故によるむちうち症を専門治療する|市川市南行徳エコルスタ整骨院
むち打ち症は

左記のようにむちのようにしなってから頚を痛める怪我です。
通常の寝違えた・・・、捻ったなどの怪我よりも
事故によるむちうち症では
頚椎の損傷度合いはとても大きいのが特徴です
酷い場合は固定具などをつけて安静にします
ですが、その後はどうでしょうか・・・
頚椎の動きはとても大事です!
人は動く動物です!
特に運動する時はとても大事です。
頚椎の動きが悪い、動いていないと
様々な部位に影響を及ぼします
- 肩こりが激しくなった・・・
- 偏頭痛が出るようになった・・・
- 四十肩、五十肩が出てきた・・・
- 腰痛や背部痛が増えた・・・など
この様な方は頚椎の動きが出ていない事が多いです!
痛みが取れるのは時間の問題です!
痛みは放っておいても取れますが
動きは戻っていない事がほとんどです。
当院では動きを取り戻す・正しく動かせるようにする事を
目標に早期回復させて行きます
事故による怪我は一瞬にして
身体が変化するのが特徴です!
筋肉の緊張やこわばりなど・・・
痛みが強い場合は筋緊張も増してます
時間がかかるケースもあります
その様な場合は提携先医療機関へ
精密検査も定期的に行って頂いております
むち打ち症でお困りの方、
交通事故だけでなく乗り物による怪我も同等です
お気軽にご相談ください

交通事故専門治療は市川市南行徳のエコルスタ整骨院で
エコルスタ整骨院では
交通事故による怪我を専門治療しております。
何故専門治療するのでしょうか??
交通事故による怪我は想像以上にダメージが大きいです!
後になって症状が出てきます。それも数年後であったり・・・。
- 事故当時は神経が興奮していて痛みなどに気づきにくい
- ムチウチ症、腰部捻挫、打撲などは通常の怪我よりも損傷は大きい
- 痛みが引いても関節や筋肉の動きは戻っていない事が多い
このようなにお悩みの方は全てエコルスタ整骨院にお任せください
- 面倒くさくて・・・
- 保険会社との手続きが分かりません・・・
- 仕事も忙しく時間が無くて・・・など
優良整骨院として評価いただいております!
当院はしっかりと治す事を目標としております
それは、数年後、十年後に
「事故による痛みが残っております・・・」と言った事を
伺う事が多く、その様になってほしくなく
しっかりと筋肉・関節を動かせるようにする治療を
ご提供したいからです。
他院のホームページによく
- 慰謝料○○○○円支払われます
- 休業補償○○○○円支払われますなど
通院するとお得です!的な表現を記載してある
ページもよくみます。
当院はそのような質の悪い表記は致しません!
痛みや辛い症状でお悩みの患者様を少しでも早く
症状を取り除く為の事しかいたしません。
通院も毎日である必要もないです。
症状が酷ければ毎日の方が良いですが
良くなってきたら間を空けて頂くようなプランで
治療計画等を患者様とご相談しながら立てて行きます
また、上記の様な事を申し上げたのも
現在は保険金不正受給者・請求者を取り締まる
専門機関も出来上がっております。
当院は優良整骨院として評価を頂いております。
症状が改善されず、長期に渡る場合は
提携先医療機関へ精密検査等も
定期的に行っております。
ご安心ください
予約制で受けられます!
痛みや・早期回復をされたい方は是非
ご相談ください
バレーボール全日本大学選抜トレーナー帯同|エコルスタはり・きゅう整骨院
今夏はバレーボール全日本大学選抜のトレーナーとして
Vリーグのサマーリーグへ参戦いたしました
大学生とはいえ、実力はプロ同等の実力はあります
トレーナーとして選手達へ意識改革や
取り組み方を伝えました
今後のパフォーマンスアップが楽しみですね
七夕
7月になりましたね。
皆様にとってはもう7月?それともまだ7月?
今年も折り返しになってきました。
7月のイベントといえば、そう。
七夕!!
短冊に思い思いの願いを書いて、笹竹に吊るす。
私もよく小さいときにわくわくしながら書いたものです。
今年の短冊の願い事は何がいいかな~と考えてるときに
ふと、思いました。
そういえば、なんで七夕のときって短冊に願い事を書くようになったんだろう...?
七夕の由来ってなんだろう...?
と。
なので、ちょっくら調べてみました!
七夕の由来は、諸説あるようですが
下記の3つの説が合わさって今の七夕になったというのが有力のようです。
1、日本古来の行事「棚機(たなばた)」
2、織姫と彦星の伝説
3、中国古来の行事「乞巧奠(きこうでん)」
1、日本古来の行事「棚機(たなばた)」
日本古来では、7月7日の夜に、秋の豊作を願ったり、人のけがれを祓う行事を行っていました。
その行事では、乙女が清らかな川のほとりの建物で、神様に着物を織っていました。
この乙女を「棚機女(たなばたつめ)」、織り機を「棚機(たなばた)」ということから7月7日を七夕(当て字である「たなばた」)と呼ぶようになったそうです。
2、織姫と彦星の伝説
七夕といえば、この伝説が有名ですね。
これは、中国からの由来が起源と言われています。
織女星(こと座のペガ)は、裁縫を司る星
牽牛星(わし座のアルタイル)は、農業を司る星
と、考えられていました。
この2つの星は、天の川を挟んで存在し、2つの星がもっとも輝くのが、旧暦の7月7日(現在の8月12日ごろ)ということから七夕伝説が生まれました。
1年でこの日だけが2つの星が輝く日ということから、織姫と彦星が巡り会うことができる日とされています。
3、中国古来の行事「乞巧奠(きこうでん)」
織姫伝説にあやかって裁縫や機織りが上手になることを願って、7月7日に行っていた中国の行事です。
裁縫の上達を願う女性たちが、庭で針に5色の糸を通し、酒肴や瓜などを祭壇に供えて、裁縫や機織りの上達を祈願しました。
七夕は、五節句の1つです。
七夕(しちせき)の節句とも呼ばれ、
3月3日の雛祭り(桃の節句)や5月5日のこどもの日(端午の節句)などと同じですね。
そして、現在の日本の七夕に欠かせない「短冊」
実は、この風習は日本でしか行われていません。
元々は、奈良時代に中国の乞巧奠(織姫にあやかって裁縫の上達を祈願する)が日本に伝わり、
江戸時代に五節句のひとつとなり、笹竹に芸事(和歌や習字など)の上達を願った短冊を書く風習が広まり、
現在では、芸事に限らず、様々なお願い事を書くようになりました。
では、なぜ笹竹に願い事を飾るのでしょうか?
竹は冬の寒さにも負けない、真っ直ぐ育つ生命力が備わっていることから、
昔から神聖な力が宿っていると信じられており、
いろんな神事に使われていました。
竹の空洞には神様が宿るなんてことも言われてたそうです。
なので、竹に願い事を飾るようになりました。
そして、「短冊の色は、5色!」
短冊は、「赤・青・黄・白・黒(紫)」の5色を使うのが一般的です。
これは、乞巧奠で5色の糸を針に通していたことが元になっています。
5色の糸が、日本では和歌を飾るのにあたり、短冊に変わったと言われています。
この5色は、古来中国の陰陽五行論に基づいた色で、
陰陽五行論とは、すべてのものは「陰・陽」の相反する2つの側面を持ち、「木・火・土・金・水」の5つの要素を根源とする説です。
木は青、火は赤、土は黄、金は白、水は黒(紫)を表しています。
それぞれ象徴するものがあり、
青(木行)は、樹木の成長する様子を象徴
赤(火行)は、光り輝く炎の様子を象徴
黄(土行)は、植物の発芽を象徴
白(金行)は、鉱物や金属を象徴
黒(水行)は、和泉から涌き出る水を象徴
この陰陽五行論は東洋医学の考え方の1つでもあり、
陰陽五行論をもとに鍼灸治療を行うこともあります。
もちろん、他の七夕飾りにも...
紙衣は、裁縫の上達
巾着は、金運
投網は、豊漁
屑籠は、整理整頓
吹き流しは、機織りの上達
などの意味があります。
毎年季節のイベントとして行う七夕ですが、
由来や意味を知るとちょこっと楽しみが増えますね
皆様の今年の七夕のお願い事は、どんな願い事を書きますか??
長文、最後まで読んでいただき有難うございました(^-^)/
院内にも七夕飾りを飾っていますので、見つけてみてくださいね
サッカー千葉県中体連トレセンのトレーニングマッチ
本日は千葉県中体連トレセンのトレーニングマッチで
私の母校八千代高校へ
人工芝になりより素晴らしい施設になりました
千葉県では公立高校初の人口芝
私もほんの一部寄付金を出しました(笑)
八千代高校サッカー部、千葉県中体連トレセンの学生達も
より一層がんばって下さい